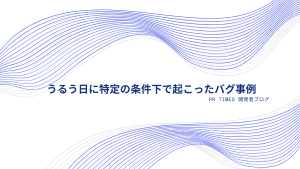こんにちは、業務委託でエンジニアの採用サポートをしている山岡(@hiro_y)です。
2020年度に新卒でエンジニアとして入社した、植江田さん、江間さん、鈴木さんの3人と一緒に開発本部の様子や、日々どのように業務と向き合っているのかを座談会の形式で話してみました。少し長くなりましたので、前編・後編に分けてお届けします。
まずは自己紹介から
山岡:まず自己紹介をお願いします。
鈴木:2020年新卒で入社しました。入社当時から主にPR TIMESサービスのフロントエンドエンジニアをやっています。
植江田:私は今、Webクリッピングというプロダクトの開発リーダーをしています。主な業務は、新しくスタートする業務の設計方針や、どう設計し実装していくかというフローを決めることです。実際に実装することもありますし、いろいろやっています。
江間:私はバックエンドでPHPを書いています。入社してからはずっとPR TIMES(https://prtimes.jp/)のバックエンド開発を行なっていて、機能追加やバグの修正をしてきました。直近では設計やAWSの構成、データベースのテーブルの設計など、ゼロからAPIの設計をやっています。
入社時から何が変わったか
山岡:入社して1年半ほど経っていると思いますが、入社時から「最も変わった」と感じることを教えてください。
鈴木:日を重ねるごとに成長している実感があります。会社組織であれば、今年プロダクト本部が立ち上がり、今は開発本部と統合になりました。エンジニアとビジネス側の架け橋ができ、コミュニケーションがスムーズかつ具体的になったことで、僕自身とても働きやすくなりました。
加えて、4月に金子さんがCTOに就任されたことで、開発本部の方向性が大きく変わって。変化が大きかった分、もちろん戸惑うこともありましたが、総じて良い方向に向かっているなと感じています。
植江田:僕は今年の8月からWebクリッピングというサービスの開発リーダーになったので、1年目と比べると体感値として業務が3倍位増えました(笑)忙しい日々を送っています。
この業務の変化に伴って、自分の技術力も凄いスピードで上がっているなという実感があるので、それは率直に嬉しいことですね。開発本部として変わったと思うのは、やはり金子さんがいらっしゃったこと。金子さんがこなければ、自分が開発リーダーになることもなかったと思います。
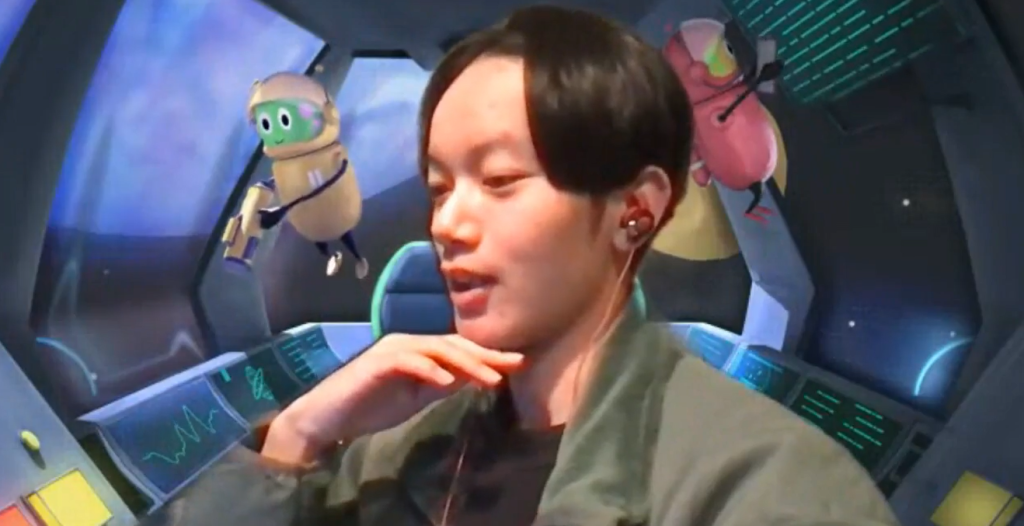
江間:僕は入社当初よりも、「ユーザーが使っているサービスを作っている」という意識が強くなりました。誰のために作っているのかを考えながら開発するように心がけています。
会社全体の視点でみれば、2人と同じで、プロダクト本部(現在は開発本部 プロダクトチーム)が新設されたことは大きくて。ここがうまく回り始めたことで、働きやすい環境になったなと感じています。
ドキュメントを残す文化へ
山岡:プロダクトチームが組織として発足したことで、動きやすくなったのはどのような部分ですか?
鈴木:以前の体制では、開発本部主導でビジネス側とコミュニケーションをとり、仕様を決める必要がありました。認識の違いが度々起こり、仕様変更も多く発生していた認識です。
プロダクトチームが出来たことで、ビジネス側とエンジニアの間に深く介入してくれるようになったので、認識のズレによるトラブルは確実に減ったと感じていますし、仕様がスムーズに決まるようになったのはとても助かっています。あとはエンジニアがやるべきことがはっきりするようになったので、全体的にプロジェクトがスムーズに進んでいくようになったと思います。

山岡:金子さんが来てこんなことが変わったというエピソードはありますか?
植江田:やっぱりドキュメントを残していくという文化ですかね。これまではチームにそういう考えがなくて。僕自身、Webクリッピングの開発リーダーになったときに何も分からない状況でした。なぜこの技術選定をしたのかなど、どこにもドキュメントが残っていない状態。憶測とコードを読みながら地道に進めていくしかない状況でした。
そういう自分の経験からも、ドキュメントを残す作業はとても重要だと感じています。今はDesign Docも書きますし、障害時は必ず報告書を残すようになりました。

タスクをこなす日々から、一歩踏み出す空気に
鈴木:僕は、金子さんが入ってくる前は、エンジニアとしてふわっとした仕事しかできていなかったですね。与えられたタスクをやるような状態。PR TIMES自体は自分から手をあげればやらせてもらえる環境ではあるんですが、開発本部の雰囲気的に、振られたタスクをこなしていくだけになっていて、正直声を上げるまで至らなかった。でも金子さんが来てから、「言えば、やっていいですよ」と。とりあえず一歩踏み出してみよう、という空気感が徐々に広まり、環境として整いつつあると感じています。
例えば最近だとフロントエンドのリプレイス時に、僕と金子さんがSlackでやりとりをしている時に新卒の2人が突然入ってきて、『興味があるので参加したいです』と。僕たちよりさらに若手でも、手を上げて意見を出してくれたことは嬉しかったですね。
江間:僕の感じているところでいうと、たとえ大きな方向転換しても(金子さんと進むことで)上手くいくという自信がついたという点です。金子さんは技術力がすごく高く、その判断はとても信頼できるものでしたが、プロジェクトが大きく方向転換して不安になる時もありました。ただその判断に従って進めていくと最終的にいい感じに進んでいく。それをこの半年ぐらいで体験していました。
山岡:旗振り役として、そういうところを金子さんはきちんとやってくれている印象です。「みんなもっといろいろなことを自主的に進めてくれていいですよ」という金子さんの考えが、皆さんにきちんと伝わってるんだなと思いました。
そんな感じで変わってきたいま、実際開発本部はどんな雰囲気ですか?
「いいサービスを届けたい」全員が思いで繋がる
鈴木:全体的に主体的な行動が増えたと思います。さきほどお話した通り、以前だと「仕事をこなす」スタンスになっていましたが、今はある程度任されているので、自分で考えて、ユーザーに届ける必要がある。もちろんこれまでも考えてきた部分ではありますが、より深く「ユーザーに届ける」という意味を僕自身考えるようになりました。
これは僕個人の変化もそうですが、皆が少しずつこの点を考えるようになったと感じています。全員がそういう雰囲気になることで、より大きい効果が生まれていくのかなと思います。
江間:僕は鈴木さんと同じチームなので、所感としてはほぼ一緒ですが、チーム全体でサービスを提供しようという意識になっているのがすごく良いと感じています。
エンジニアとデザイナー、PdMがフラットな立場で『どうやったらもっと良いサービスを作れるか』とか『ユーザーに価値を提供できるか』というところをしっかり議論して進んでいると思います。

植江田:それでいうとWebクリッピングチームは二人と少し状況が違くて、まだまだこれからですかね。自分からこれが必要なんじゃないですか、と声を上げるメンバーがまだおらず、すべて僕がタスクを決めている状況。チームができてから日が浅いというのもありますが、これから空気づくり含めてやっていきたいです。
先輩の背中を見て“雑談力”を向上
山岡:技術的なサポートとして業務委託のuzullaさんが入っている影響は、皆さんはどう感じていますか?
植江田:クリッピングは9月に大きなインシデント起こしてたのですが、うずらさんにはめちゃくちゃ助けていただきました。最初の1週間くらいはほぼ僕1人で実装をしていて、正直とてもしんどかった。
途中からuzullaさんがサポートに入ってくださるようになって、技術的な側面だけでなく、雰囲気も明るくしてくださるので、僕としてはuzullaさんがいたから何とか乗り越えられたと思っています。
江間:技術力は言わずもがなで、すごく恩恵を受けています。雰囲気面においては、Slackで沢山話しているuzullaさんをみて、自分自身も気軽に発言しやすくなった実感があります。1ヶ月間のSlackのアナリティクスでは、uzullaさんが投稿されたメッセージが一番多いらしいです(笑)
コミュニケーションや雑談が大事だということはuzullaさんもよくおっしゃっていて。自分もそう感じていて、uzullaさんの雰囲気づくりやコミュニケーションを参考にさせてもらっています。

鈴木:コミュニケーションの面で言うと、あのつぶやく感じとかが最初はなんだろう…?と思ってたんですが(笑)。実際チームに効果があるのを見ていて感じます。
僕はまだ遠慮してしまうところもあるので、自分からコミュニケーションを積極的に取る姿勢を学ばせていただいていますね。

<後編へ続く>
執筆協力=倉本亜里沙、編集協力=田代くるみ(Qurumu)